日付 :2015年5月9日(土)
山名 :鈴鹿 竜ヶ岳
コースタイム:宇賀渓キャンプ場 8:50 金山尾根分岐9:30 県境三叉路11:30 竜ヶ岳頂上12:00~12:30 遠足尾根・裏道分岐 13:0 0 遠足尾根出口15:00 宇賀渓キャンプ場15:30
昨年の12月冬季の天狗堂/君ヶ畑にいった時、天狗堂から雪に被った鈴鹿の主脈である藤原岳・静ケ岳そして竜ヶ岳の山々を眺めていた。この竜ヶ岳は、三重県いなべ市と滋賀県東近江市の境にある標高1,099mのたおやかな山である。竜が寝そべっているような丸味を帯びた山容から、その名がついたと言われている。いずれこの山にも訪れ、鈴鹿山系の足跡の空白部を埋めたいと思っていた、そんな矢先に実現した。
滋賀県側から竜ヶ岳へ登るには石槫(いしぐれ)峠まで自動車で乗りつけるのが、最短である。今回計画されたのは、数年前開通された石槫トンネルを通り、この山の登山基地である宇賀渓へ赴くことになった。ホタガ谷を囲むように位置する金山尾根を登り、下山は東に張り出している長大な遠足尾根を辿ることになった。
この頃、どこの山に行っても中高年のグループで占められているのだが、宇賀渓観光案内所の前には、若い山ガール達のグループ、若い男女のペアー 学生グループなど多くの若者がつどっていた。
我々のザックの容量は精々30リットル以下。学生グループは70リットル以上の大型ザックである。このザックに何本もの水を注入したペットボトルを入れたり出したりしていた。一本毎の重みを感じながら、錬成に耐えられる重量になったか、おしはかっていた。最後に勇気を奮い立たせて全てを詰め込み、介添えをしてもらいやっと立ち上がった。自力では到底立てない重量である。これから竜ヶ岳から治田峠を越えて縦走すると言っていた。 出発前の不安を伴った緊張感が漂う若者を見ながら、私の遠い昔の姿が蘇ってきた・・・・・。
我々も宇賀渓のキャンプ場の橋を渡って、車道を進み魚止橋を渡り、金山尾根登山道の取りつきから頂上を目指した。宇賀渓観光案内所で貰った子細に書き込まれた「宇賀渓登山道 位置確認№(七大字生産森林組合)」に導かれながら進んだ。この間30ケほどの充分過ぎる案内板があった。
やがて、山道の勾配も緩み、笹原となって、頂上が近づいてきたことが分かった。




昼食後雲行きも怪しなり、小雨がパラついてきたので、休憩もそこそこにして下山にかかった。遠足尾根の杉植林帯の急傾斜をジグザグに下って行くと山野草に出会った。見た瞬間、エビネと分かった。
放射状に広がった葉っぱに、葉脈が伸長方向に走り、がっしりとした株の真ん中から「すーと」と伸びた花茎に花を付けていた。
その姿は目を引くような華やかではなく、控え目である。古風で、凛とした気品が漂っていた。
エビネに出会うことさえ無いこの頃であったが、40~50株のエビネの大群落に出会えたことは、驚きであり幸運であった。「鈴鹿山系に、そのままの自然がまだ残されていた」、とつくづく感じ入った。
この一帯は腐葉土が堆積し、適度の湿りのある柔らかい肥えた土があり、適度の日光が射し込んでいた。本来、条件さえ揃えばエビネは大繁殖するものである。 一昔前、山野の林床にエビネが多く見られた。神社に通じる山道、田んぼのあぜ道、畑に隣接する雑木林などいわゆる里山にも自生していた。かつてエビネは身近な野草であったが、殆どその姿を消してしまった。
エビネの花の色には赤、緑、黄、茶があり、これらの色の混合色がある。この複雑な花色に目を付けた収集家が「身近に置きたい」と言う、身勝手な欲望を満たすため、持ち帰ったためである。更に、無菌培養で交配させ、多彩な色の花に仕立てていった。その結果、高値で取引されている。人は罪深いものである。
また何時の日か、ここを訪れた時、このエビネの群落が変わらぬ姿でいてほしいものである。



山名 :鈴鹿 竜ヶ岳
コースタイム:宇賀渓キャンプ場 8:50 金山尾根分岐9:30 県境三叉路11:30 竜ヶ岳頂上12:00~12:30 遠足尾根・裏道分岐 13:0 0 遠足尾根出口15:00 宇賀渓キャンプ場15:30
昨年の12月冬季の天狗堂/君ヶ畑にいった時、天狗堂から雪に被った鈴鹿の主脈である藤原岳・静ケ岳そして竜ヶ岳の山々を眺めていた。この竜ヶ岳は、三重県いなべ市と滋賀県東近江市の境にある標高1,099mのたおやかな山である。竜が寝そべっているような丸味を帯びた山容から、その名がついたと言われている。いずれこの山にも訪れ、鈴鹿山系の足跡の空白部を埋めたいと思っていた、そんな矢先に実現した。
滋賀県側から竜ヶ岳へ登るには石槫(いしぐれ)峠まで自動車で乗りつけるのが、最短である。今回計画されたのは、数年前開通された石槫トンネルを通り、この山の登山基地である宇賀渓へ赴くことになった。ホタガ谷を囲むように位置する金山尾根を登り、下山は東に張り出している長大な遠足尾根を辿ることになった。
この頃、どこの山に行っても中高年のグループで占められているのだが、宇賀渓観光案内所の前には、若い山ガール達のグループ、若い男女のペアー 学生グループなど多くの若者がつどっていた。
我々のザックの容量は精々30リットル以下。学生グループは70リットル以上の大型ザックである。このザックに何本もの水を注入したペットボトルを入れたり出したりしていた。一本毎の重みを感じながら、錬成に耐えられる重量になったか、おしはかっていた。最後に勇気を奮い立たせて全てを詰め込み、介添えをしてもらいやっと立ち上がった。自力では到底立てない重量である。これから竜ヶ岳から治田峠を越えて縦走すると言っていた。 出発前の不安を伴った緊張感が漂う若者を見ながら、私の遠い昔の姿が蘇ってきた・・・・・。
我々も宇賀渓のキャンプ場の橋を渡って、車道を進み魚止橋を渡り、金山尾根登山道の取りつきから頂上を目指した。宇賀渓観光案内所で貰った子細に書き込まれた「宇賀渓登山道 位置確認№(七大字生産森林組合)」に導かれながら進んだ。この間30ケほどの充分過ぎる案内板があった。
やがて、山道の勾配も緩み、笹原となって、頂上が近づいてきたことが分かった。
帰路に通る笹原を望む

たおやかな竜ヶ岳の頂上へ続く道

近江側の山々の眺望

手前が静ケ岳、 奥が御池岳

昼食後雲行きも怪しなり、小雨がパラついてきたので、休憩もそこそこにして下山にかかった。遠足尾根の杉植林帯の急傾斜をジグザグに下って行くと山野草に出会った。見た瞬間、エビネと分かった。
放射状に広がった葉っぱに、葉脈が伸長方向に走り、がっしりとした株の真ん中から「すーと」と伸びた花茎に花を付けていた。
その姿は目を引くような華やかではなく、控え目である。古風で、凛とした気品が漂っていた。
エビネに出会うことさえ無いこの頃であったが、40~50株のエビネの大群落に出会えたことは、驚きであり幸運であった。「鈴鹿山系に、そのままの自然がまだ残されていた」、とつくづく感じ入った。
この一帯は腐葉土が堆積し、適度の湿りのある柔らかい肥えた土があり、適度の日光が射し込んでいた。本来、条件さえ揃えばエビネは大繁殖するものである。 一昔前、山野の林床にエビネが多く見られた。神社に通じる山道、田んぼのあぜ道、畑に隣接する雑木林などいわゆる里山にも自生していた。かつてエビネは身近な野草であったが、殆どその姿を消してしまった。
エビネの花の色には赤、緑、黄、茶があり、これらの色の混合色がある。この複雑な花色に目を付けた収集家が「身近に置きたい」と言う、身勝手な欲望を満たすため、持ち帰ったためである。更に、無菌培養で交配させ、多彩な色の花に仕立てていった。その結果、高値で取引されている。人は罪深いものである。
また何時の日か、ここを訪れた時、このエビネの群落が変わらぬ姿でいてほしいものである。
遠足尾根に自生しているエビネ


宇賀渓キャンプ場~竜ヶ岳GPSの足跡

歳を重ねてきても、自分を自然の中に置くようにしている。それも高山に出かけるより、身近な三上山に出向くことが多くなった。この山、結構岩場が多い。何回も訪れていると、どこに岩があり、足をどう運べば、最も簡単に登り切れるかまで分かってくるものだ。何より、しみじみとした四季の移ろいも楽しみにしている。
生命あふれる初夏の季節になると、三上山のあっちこっちで、「シダ」が一斉に芽吹いてくる。中でも、希望が丘側の裾野の林床には、溢れんばかりに生い茂り、脇役が主役になっていた。
昨年までの濃い深緑色の葉色をした親の葉っぱから、一本の茎が、立ち上がり、その先端から新たに左右に一対の葉がすらりと伸びていた。この一帯は若葉によって黄緑色の大海原となっていた。 シダとは、葉が垂れている姿と結びついて「下垂れる」という意味である。が、この溌剌として伸び盛りの若葉の姿は、横に限りなく真っ直ぐであった。
一つひとつの若葉が、一斉に私を見詰めるようで嬉しくなる。時たま「イケズ」な向きをしているものもあるが、人間ほどでない。お互い僅かな光を分けあって住み分けながら、日が射す方向に行儀よく開いていた。
いずれの角度も同じ120度位であった。規則正しく同じ角度をしているのは、この植物にとっては大事なことなのであろう。この幾何学模様は神秘に満ち溢れていた。このようにして毎年葉を延ばし、2枚の葉の段が何世代か積み上がっていた。 写真に切り取った光景は、何時頃から始まったのであろうか。私の一生だけ ・・・。いや気の遠くなるほど太古から繰り返されてきた光景なのであろう。昨日今日、知った私が、あれこれ詮索するのが、烏滸がましい。
この山に来ると、色んな人に出会う。子供ずれの家族一家のハイキング、本格的な登山前のトレーニングで来る人、日課として来る人といろいろだ。私は、身体を鍛えるのでなく、ただ健康を維持するためである。
美しさに目を奪われ、シダの写真を懸命に撮っていると、「何を調べておられるのですか」と知人が近寄ってきた。
「シダだヨ」と返答すると、
葉っぱをひっくり返しながら「シダに違いないが、裏が白いので、ウラジロ」と呼ばれていると教えてくれた。
裏が白いとは、日本人の大切な心がけを表している言葉。正月飾りに使われている、あのウラジロであった。

生命あふれる初夏の季節になると、三上山のあっちこっちで、「シダ」が一斉に芽吹いてくる。中でも、希望が丘側の裾野の林床には、溢れんばかりに生い茂り、脇役が主役になっていた。
昨年までの濃い深緑色の葉色をした親の葉っぱから、一本の茎が、立ち上がり、その先端から新たに左右に一対の葉がすらりと伸びていた。この一帯は若葉によって黄緑色の大海原となっていた。 シダとは、葉が垂れている姿と結びついて「下垂れる」という意味である。が、この溌剌として伸び盛りの若葉の姿は、横に限りなく真っ直ぐであった。
一つひとつの若葉が、一斉に私を見詰めるようで嬉しくなる。時たま「イケズ」な向きをしているものもあるが、人間ほどでない。お互い僅かな光を分けあって住み分けながら、日が射す方向に行儀よく開いていた。
いずれの角度も同じ120度位であった。規則正しく同じ角度をしているのは、この植物にとっては大事なことなのであろう。この幾何学模様は神秘に満ち溢れていた。このようにして毎年葉を延ばし、2枚の葉の段が何世代か積み上がっていた。 写真に切り取った光景は、何時頃から始まったのであろうか。私の一生だけ ・・・。いや気の遠くなるほど太古から繰り返されてきた光景なのであろう。昨日今日、知った私が、あれこれ詮索するのが、烏滸がましい。
この山に来ると、色んな人に出会う。子供ずれの家族一家のハイキング、本格的な登山前のトレーニングで来る人、日課として来る人といろいろだ。私は、身体を鍛えるのでなく、ただ健康を維持するためである。
美しさに目を奪われ、シダの写真を懸命に撮っていると、「何を調べておられるのですか」と知人が近寄ってきた。
「シダだヨ」と返答すると、
葉っぱをひっくり返しながら「シダに違いないが、裏が白いので、ウラジロ」と呼ばれていると教えてくれた。
裏が白いとは、日本人の大切な心がけを表している言葉。正月飾りに使われている、あのウラジロであった。
気に入るまで撮り続けた中の1枚写真

私は滋賀県の在住者だが、カタクリ草は、群生している規模と言い、一つひとつの大きさも、当県より福井県の方が優れていると思っていたので、桜の咲くころになると、福井に足が向いてしまう。 今回は鯖江市と福井市の境に連なる文殊山へ向かった。
問題は、ここに行く交通の便が悪さだ。一時間当たりの列車本数が1本多くて2本。その上、青春きっぷを活用したので、トータル10時間を要してしまった。でもいいこともある。この特別格安きっぷによる交通費は、二分の一、特急券を使ったとして三分の一で済んだことだ。 たまたまだが、北鯖江駅に降り立つと、山仲間の知人のグループで出会った。我々と同じような考え方して、福井のカタクリの開花時期に合わせた青春きっぷを利用していた。
日付: 4月4日(土)
山名: 文殊山
コース: JR北鯖江駅(10:00)~酒清水参道口(10:20)~橋立山(11:20)
~350m三角点(奥の院)(12:10)~文殊山本堂(13:10)~
二上駐車場(14:30)~JR大士呂駅(15:17)
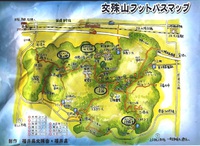 制作 福井県文殊会・福井県の地図によると、登山口は10カ所ほどある。その中で、JR北鯖江駅を出発し次の大士呂駅に帰着する事を前提に、橋立山から文殊山を縦走し、二上コースを下山する最も長いルートを辿った。
制作 福井県文殊会・福井県の地図によると、登山口は10カ所ほどある。その中で、JR北鯖江駅を出発し次の大士呂駅に帰着する事を前提に、橋立山から文殊山を縦走し、二上コースを下山する最も長いルートを辿った。
清水参道口~橋立山の間は、人に出会わなかったが、奥の院~文殊山では大勢の人で賑わっていた。
「ここには毎日来ています」、と地元の人が話しかけてきた。「どうして」と返事をするとにやりとしていた。少ししてから解ったのだが、文殊山の標高は365m。この数値の語呂合わせで365日だった。また、文殊山本堂で店を開いていたオジサンは「この10年で花山として人気になり、訪れる人が増えた」、と言っておられた。
目当てのカタクリ草は小さな群落が、あちらこちらに見られた、文殊山周辺では大きな群落をつくっていた。最近山野草といえども、管理下の庇護のもとに育てられ、野性味が欠ける傾向がみられるが、ここではロープも張られていない、なすがままの野趣にあふれていた。
この一帯はカタクリ草に混じって数々の山野草にも出会った。仲間は、日ごろ蓄えてきた山野草の知識を競うように次から次へと山野草を見出しては、名前を言い当てていた。
春蘭・猫の目草・イカリソウ・ ショウジョバカマ・キクザキイチゲソウ・エンレイソウ・各種のスミレ・ヒメニラ・ヤマエンゴサク・ヤマワサビ・タムシバ・・・・・・などきりがない。
私は名前がわからないけど、一度や二度出合い馴染のある花もあった。花談義に加わることが出来たのは、モクレンの花に似たタムシバかコブシの見分け方だけであった。結局葉っぱが見られなかったので、タムシバだった。
問題は、ここに行く交通の便が悪さだ。一時間当たりの列車本数が1本多くて2本。その上、青春きっぷを活用したので、トータル10時間を要してしまった。でもいいこともある。この特別格安きっぷによる交通費は、二分の一、特急券を使ったとして三分の一で済んだことだ。 たまたまだが、北鯖江駅に降り立つと、山仲間の知人のグループで出会った。我々と同じような考え方して、福井のカタクリの開花時期に合わせた青春きっぷを利用していた。
日付: 4月4日(土)
山名: 文殊山
コース: JR北鯖江駅(10:00)~酒清水参道口(10:20)~橋立山(11:20)
~350m三角点(奥の院)(12:10)~文殊山本堂(13:10)~
二上駐車場(14:30)~JR大士呂駅(15:17)
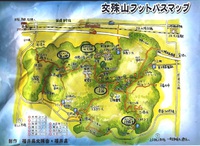 制作 福井県文殊会・福井県の地図によると、登山口は10カ所ほどある。その中で、JR北鯖江駅を出発し次の大士呂駅に帰着する事を前提に、橋立山から文殊山を縦走し、二上コースを下山する最も長いルートを辿った。
制作 福井県文殊会・福井県の地図によると、登山口は10カ所ほどある。その中で、JR北鯖江駅を出発し次の大士呂駅に帰着する事を前提に、橋立山から文殊山を縦走し、二上コースを下山する最も長いルートを辿った。清水参道口~橋立山の間は、人に出会わなかったが、奥の院~文殊山では大勢の人で賑わっていた。
「ここには毎日来ています」、と地元の人が話しかけてきた。「どうして」と返事をするとにやりとしていた。少ししてから解ったのだが、文殊山の標高は365m。この数値の語呂合わせで365日だった。また、文殊山本堂で店を開いていたオジサンは「この10年で花山として人気になり、訪れる人が増えた」、と言っておられた。
目当てのカタクリ草は小さな群落が、あちらこちらに見られた、文殊山周辺では大きな群落をつくっていた。最近山野草といえども、管理下の庇護のもとに育てられ、野性味が欠ける傾向がみられるが、ここではロープも張られていない、なすがままの野趣にあふれていた。
この一帯はカタクリ草に混じって数々の山野草にも出会った。仲間は、日ごろ蓄えてきた山野草の知識を競うように次から次へと山野草を見出しては、名前を言い当てていた。
春蘭・猫の目草・イカリソウ・ ショウジョバカマ・キクザキイチゲソウ・エンレイソウ・各種のスミレ・ヒメニラ・ヤマエンゴサク・ヤマワサビ・タムシバ・・・・・・などきりがない。
私は名前がわからないけど、一度や二度出合い馴染のある花もあった。花談義に加わることが出来たのは、モクレンの花に似たタムシバかコブシの見分け方だけであった。結局葉っぱが見られなかったので、タムシバだった。
文殊山本堂 文殊山の山並み


カタクリ草は日が昇ると、人だったら背骨が砕けるほど、「これでもか」と弓なりに反り返る。この姿を期待していた。あいにく、曇り模様で、元気いっぱいの姿を見ることが出来なかったのが残念。
自生している曇り模様のカタクリ草群落

 同じ色をした山野草の群落は圧巻である。見飽きるわけでもないが、その中で変わった色を探したくなるものである。でも、求めると中々出合うことが出来ないものだ。
同じ色をした山野草の群落は圧巻である。見飽きるわけでもないが、その中で変わった色を探したくなるものである。でも、求めると中々出合うことが出来ないものだ。以前、高山植物の女王とよばれているコマクサがピンク色の花を付けて群生していた中で、いとも簡単に白いコマクサに出会ったことがあった。同じように、カタクリもピンク色をしているのだが、以前からシロバナカタクリを探し求めていた。カタクリの花と今庄(藤倉山)
今回は蕾であったが、シロバナカタクリに出合えたのは幸運であった。
野菜を育てていると、避けて通れないのが、草引きである。春先は苦にならない。が、その内、草を引いても、引いてもおっつかなくなる。
そんな中、一冊の本に出合った。「雑草は踏まれても諦めない」である。この本は、踏まれても立ち上がってくる逞しい雑草について語られており、逆境に負けない生き方に憧れを抱いたサラリーマンにも読まれているようだ。
 私は、50坪ほどの家庭菜園をしているので、植物についての書籍を図書館で何冊も目を通していた。そんな折、独特の語り口の書籍があった。植物の生き方・生存の方法について、人間ではなく植物の目線から書かれていた。今から思えば、稲垣栄洋氏が執筆されたユニークな書籍を、かなり前から読んでいたようだ。
私は、50坪ほどの家庭菜園をしているので、植物についての書籍を図書館で何冊も目を通していた。そんな折、独特の語り口の書籍があった。植物の生き方・生存の方法について、人間ではなく植物の目線から書かれていた。今から思えば、稲垣栄洋氏が執筆されたユニークな書籍を、かなり前から読んでいたようだ。
雑草とは何かを、「雑草は踏まれても諦めない」から引用してみる。
「ニンジン畑に生えてきたジャガイモ は雑草なのか」との問いに
ニンジンを栽培する立場から言えば、それ以外に生えてくるものはすべて邪魔者だ。だから、ニンジン畑のジャガイモは紛れもなく雑草なのである。
しかし、こんな考え方もある。「ニンジンばかりか、ジャガイモまで収穫できる。やれ儲かった」
要は、雑草と言う定義は、考え方しだい。つまり、雑草と言う概念は曖昧でくだらない分類であることを知らされた。 したがって、雑草と言わずに、「野草」と言うべきかもしれない。
また、雑草は、畑が居心地よく、むしろここに住み着いていると述べている。
自然界では沢山の植物の競争相手がいるので、雑草は片隅に追いやられた。しかし、人間がつくり上げた田んぼ、畑、道端、空き地に入り込んできて、はじめて繁栄できたと説いている。そこでは、いつも刈られたり、踏まれて住みにくいと思われるのだが、雑草はそれぞれ個性ある生き延びる戦略・戦術を駆使している。オオバコは「ふまれる」ことで殖えていく、シバの刈り取られてもびくともしない茎の構造・・・・・など興味深い切り口で語られていた。
単に、雑草を敵視するだけでなく、少し親近感をもって、わが畑に生えてくる雑草を徹底的に観察し、敵の正体を知る事にした。
冬の畑は、取り立てた作物の生長もないので、放置気味である。3月上旬になると、まだ肌寒いが、畑の畝と畝間の吹き溜まりは、温かい。冷たい風が吹き荒れていても、僅かな陽だまりは、居心地がいいのであろう。そこにちゃっかりと花を咲かしていた。名前は「オオイヌノフグリ」である。
意味不明の長い名前なので覚えにくい。 オオイヌの「フグリ」とはどういう意味なのか調べてみると、新しい国語辞典には載っていなかったが、かなり古い辞典には「陰嚢」と書いてあった。要するに、花の後につく実が2つ並んでいる形状が、雄犬の「フグリ」、つまり金玉に似ていることから命名したようだ。一方では、可愛い「ベロニカ」ともいう。
普通の植物は、太陽光を求め背丈を競って生長するものだが、オオイヌノフグリは、冬から早春にかけて、人目にもつかないように地面を這うように茎を伸ばし、多数の花を咲かせていた。春の終わりには、人に迷惑をかけないように姿をさっさと消してしまう、この処し方は見事である。他の植物が繁茂する夏場は苦手なのであろ、夏は、種で過ごすようだ。
畑の畝と畝間の陽だまりに繁茂している「オオイヌノフグリ」


日が射さない時の閉花状態 日が射した時の開花状態
 虫が寄ってきた「オオイヌノフグリ」
虫が寄ってきた「オオイヌノフグリ」
 オオイヌノフグリの花びらは何気なく咲いていると思われているが、実は昆虫を呼ぶための知恵に溢れていると、語っている。
オオイヌノフグリの花びらは何気なく咲いていると思われているが、実は昆虫を呼ぶための知恵に溢れていると、語っている。
日が射していない時には、5mm程度の蕾状態であったが、日が射してくると花びらは一斉に10mmまで開いた。 太陽の光を巧みに集めるパラボラアンテナのようになっていて、花の中の温度を上げている。花弁の中は長い冬を過ごした虫たちにとって、天国になるのであろう。
4枚のコバルトブルーの花びらには中央に向かって濃い瑠璃色の筋が中心に向かっているのが見られる。人が美しい模様と感じるためにつくっているのではなく、虫を蜜のある一番奥まで誘導するためのガイドラインである。 無論、オオイヌノフグリが次世代に命を繋ぐための受粉を促すためである。
そんな中、一冊の本に出合った。「雑草は踏まれても諦めない」である。この本は、踏まれても立ち上がってくる逞しい雑草について語られており、逆境に負けない生き方に憧れを抱いたサラリーマンにも読まれているようだ。
 私は、50坪ほどの家庭菜園をしているので、植物についての書籍を図書館で何冊も目を通していた。そんな折、独特の語り口の書籍があった。植物の生き方・生存の方法について、人間ではなく植物の目線から書かれていた。今から思えば、稲垣栄洋氏が執筆されたユニークな書籍を、かなり前から読んでいたようだ。
私は、50坪ほどの家庭菜園をしているので、植物についての書籍を図書館で何冊も目を通していた。そんな折、独特の語り口の書籍があった。植物の生き方・生存の方法について、人間ではなく植物の目線から書かれていた。今から思えば、稲垣栄洋氏が執筆されたユニークな書籍を、かなり前から読んでいたようだ。雑草とは何かを、「雑草は踏まれても諦めない」から引用してみる。
「ニンジン畑に生えてきたジャガイモ は雑草なのか」との問いに
ニンジンを栽培する立場から言えば、それ以外に生えてくるものはすべて邪魔者だ。だから、ニンジン畑のジャガイモは紛れもなく雑草なのである。
しかし、こんな考え方もある。「ニンジンばかりか、ジャガイモまで収穫できる。やれ儲かった」
要は、雑草と言う定義は、考え方しだい。つまり、雑草と言う概念は曖昧でくだらない分類であることを知らされた。 したがって、雑草と言わずに、「野草」と言うべきかもしれない。
また、雑草は、畑が居心地よく、むしろここに住み着いていると述べている。
自然界では沢山の植物の競争相手がいるので、雑草は片隅に追いやられた。しかし、人間がつくり上げた田んぼ、畑、道端、空き地に入り込んできて、はじめて繁栄できたと説いている。そこでは、いつも刈られたり、踏まれて住みにくいと思われるのだが、雑草はそれぞれ個性ある生き延びる戦略・戦術を駆使している。オオバコは「ふまれる」ことで殖えていく、シバの刈り取られてもびくともしない茎の構造・・・・・など興味深い切り口で語られていた。
単に、雑草を敵視するだけでなく、少し親近感をもって、わが畑に生えてくる雑草を徹底的に観察し、敵の正体を知る事にした。
冬の畑は、取り立てた作物の生長もないので、放置気味である。3月上旬になると、まだ肌寒いが、畑の畝と畝間の吹き溜まりは、温かい。冷たい風が吹き荒れていても、僅かな陽だまりは、居心地がいいのであろう。そこにちゃっかりと花を咲かしていた。名前は「オオイヌノフグリ」である。
意味不明の長い名前なので覚えにくい。 オオイヌの「フグリ」とはどういう意味なのか調べてみると、新しい国語辞典には載っていなかったが、かなり古い辞典には「陰嚢」と書いてあった。要するに、花の後につく実が2つ並んでいる形状が、雄犬の「フグリ」、つまり金玉に似ていることから命名したようだ。一方では、可愛い「ベロニカ」ともいう。
普通の植物は、太陽光を求め背丈を競って生長するものだが、オオイヌノフグリは、冬から早春にかけて、人目にもつかないように地面を這うように茎を伸ばし、多数の花を咲かせていた。春の終わりには、人に迷惑をかけないように姿をさっさと消してしまう、この処し方は見事である。他の植物が繁茂する夏場は苦手なのであろ、夏は、種で過ごすようだ。
畑の畝と畝間の陽だまりに繁茂している「オオイヌノフグリ」


日が射さない時の閉花状態 日が射した時の開花状態

 虫が寄ってきた「オオイヌノフグリ」
虫が寄ってきた「オオイヌノフグリ」 オオイヌノフグリの花びらは何気なく咲いていると思われているが、実は昆虫を呼ぶための知恵に溢れていると、語っている。
オオイヌノフグリの花びらは何気なく咲いていると思われているが、実は昆虫を呼ぶための知恵に溢れていると、語っている。 日が射していない時には、5mm程度の蕾状態であったが、日が射してくると花びらは一斉に10mmまで開いた。 太陽の光を巧みに集めるパラボラアンテナのようになっていて、花の中の温度を上げている。花弁の中は長い冬を過ごした虫たちにとって、天国になるのであろう。
4枚のコバルトブルーの花びらには中央に向かって濃い瑠璃色の筋が中心に向かっているのが見られる。人が美しい模様と感じるためにつくっているのではなく、虫を蜜のある一番奥まで誘導するためのガイドラインである。 無論、オオイヌノフグリが次世代に命を繋ぐための受粉を促すためである。
3月初旬、可憐な姿をしたフキのトウが姿を現した。舗装道路の割れ目から。
蕗の薹にとっては、決して好んだ場所ではない。
でも、種がここに落ちた時から、ここで、一生を生き延びなければならない。
だから、植物の限りない忍耐強さに、人が魅了される。

早春を知らせるふきのとう
蕗の薹にとっては、決して好んだ場所ではない。
でも、種がここに落ちた時から、ここで、一生を生き延びなければならない。
だから、植物の限りない忍耐強さに、人が魅了される。

早春を知らせるふきのとう
今では、菩提寺山を知っている人が少ないようだが、歌川広重の石部宿の田楽茶屋「いせや」には、菩提寺山が大きく描かれ、遠くに小さく三上山。当時の旅人にとっては、この菩提寺山が一つの目安になっていた。
この山を下山後、その山麓の住宅街を歩いていた時、刈り込んだ生垣を越えてにょきにょきと突っ立っている植物があった。一回だけでなく、あっちこっちで目にした。
希望が丘の自然観察会の先生Hさんは「この植物の名前しっているか」と問いかけてきた。
咄嗟に聞かれ、花も咲いていない茎と葉っぱでは、全く予測もできなかった。
仲間の一人がそっと、おしえてくれた。
「皇帝ダリア」だ。 茎が木質化した木立のようにデカいので 、別名木立ダリアとも呼ばれている。
さて、その後我が家の庭にも同じように、にょきにょきと突っ立つ茎に、いっぱいの花を付けました。 そうなんです。皇帝ダリアでした。
こういう事を「看脚下」と言うのだろう・・・・

この山を下山後、その山麓の住宅街を歩いていた時、刈り込んだ生垣を越えてにょきにょきと突っ立っている植物があった。一回だけでなく、あっちこっちで目にした。
希望が丘の自然観察会の先生Hさんは「この植物の名前しっているか」と問いかけてきた。
咄嗟に聞かれ、花も咲いていない茎と葉っぱでは、全く予測もできなかった。
仲間の一人がそっと、おしえてくれた。
「皇帝ダリア」だ。 茎が木質化した木立のようにデカいので 、別名木立ダリアとも呼ばれている。
さて、その後我が家の庭にも同じように、にょきにょきと突っ立つ茎に、いっぱいの花を付けました。 そうなんです。皇帝ダリアでした。
こういう事を「看脚下」と言うのだろう・・・・
晩秋に咲いた我が家の皇帝ダリア

野山を駆け巡っていると、色んな山野草に出合うものです。花を咲かせると、今まで辺りにひっそりと溶け込んでいた山野草は、にわかにその姿を露わにし始めるのです。元々、花は、その存在を知らせたいのでしょう。目立ちたがり屋なのです。色合であり、匂いであり、さらに、かわった形をしていることもあります。
”ホタルブクロ”は、釣り鐘状をした花を下向きに咲かせ、風情ある姿をしています。それ以上に花名が素晴らしい。この袋の中にホタルが入り、点滅しながら青白く輝くホタルが、飛交う様を思い浮かべることができます。幼いころ、夢見たファンタジーの世界がふつふつと湧いてきます。
かって、野洲川の河口部は、南流と北流に分かれていました。ここに出来た中洲には、「竹生」の地名が付けられました。堤防には、野洲川の堤防を守るために沢山の竹が植えられました名残です。現在も竹藪を見ることができます。 この河辺林は、豊かな手つかずの自然が広がっています。
ここで、草むらの中に、僅か数輪ですが、”ホタルブクロ”を発見しました。
ボランティアで竹藪の整備をしている作業仲間から、「この花、何という花か」と尋ねられました。
咄嗟の質問でしたが、「ホタルブクロだ」と意外にもすらすらと答えられ、我ながら戸惑ってしまいました。
今までホタルブクロはすでには、何回も出会っていました。最初に出合ったのが、数年前、湖北の横岳でした。それも紅葉の頃に寂しく一輪咲いていました。ホタルブクロの名の通り花が咲くのは、蛍の飛ぶ頃、梅雨の時期なのに、秋に狂い咲きしていました。そのギャップがとても印象深く、花名を覚えるきっかけとなりました。

”ホタルブクロ”は、釣り鐘状をした花を下向きに咲かせ、風情ある姿をしています。それ以上に花名が素晴らしい。この袋の中にホタルが入り、点滅しながら青白く輝くホタルが、飛交う様を思い浮かべることができます。幼いころ、夢見たファンタジーの世界がふつふつと湧いてきます。
かって、野洲川の河口部は、南流と北流に分かれていました。ここに出来た中洲には、「竹生」の地名が付けられました。堤防には、野洲川の堤防を守るために沢山の竹が植えられました名残です。現在も竹藪を見ることができます。 この河辺林は、豊かな手つかずの自然が広がっています。
ここで、草むらの中に、僅か数輪ですが、”ホタルブクロ”を発見しました。
ボランティアで竹藪の整備をしている作業仲間から、「この花、何という花か」と尋ねられました。
咄嗟の質問でしたが、「ホタルブクロだ」と意外にもすらすらと答えられ、我ながら戸惑ってしまいました。
今までホタルブクロはすでには、何回も出会っていました。最初に出合ったのが、数年前、湖北の横岳でした。それも紅葉の頃に寂しく一輪咲いていました。ホタルブクロの名の通り花が咲くのは、蛍の飛ぶ頃、梅雨の時期なのに、秋に狂い咲きしていました。そのギャップがとても印象深く、花名を覚えるきっかけとなりました。
野洲川の河辺林に咲いていた ”ホタルブクロ”

既に、2009年06月26日 カキツバタ 平池に訪れていたが、再び、6月18日(火)カキツバタに会いに行った。
濃い紫色のカキツバタが咲く平池は、高木のスギ林に囲まれ、深山の様相を漂う光景は、北欧さえ感じる。森全体が静寂を保ち、冷気とともに、精霊の存在を信じさせる。何回来ても、心が落ち着くところ。


濃い紫色のカキツバタが咲く平池は、高木のスギ林に囲まれ、深山の様相を漂う光景は、北欧さえ感じる。森全体が静寂を保ち、冷気とともに、精霊の存在を信じさせる。何回来ても、心が落ち着くところ。


親しい友人から一枚の写真が携帯に送られてきた。鈴鹿に自生している”クマガイソウ”の写真である。この幻の山野草について、私は、3~4年前から、探しに行く機会を狙っていた。が、もう一つ正確な場所が分からなかったこと、花が咲く、この時期に”やまひる”の襲撃も多少気になり、躊躇(ちゅうちょ)していた。
今回は、写真付きでコグルミ谷で密かに群生している場所を正確に伝えてくれたので、5月31日(金)、山野草を愛でている友人を誘って出かける気になった。
このコグルミ谷に行くには、滋賀県と三重県を結んでいる国道306号線の鞍掛峠を通過しなければならない。だが、昨年9月17、18日の大雨により道路が崩落し、通行止めとなっていた。仕方なく、滋賀県側の鞍掛峠駐車場に自動車を止め、コグルミ谷 の出合にむかった。

滋賀側のトンネルまでは通行可能だが、三重側の道路上には土石が散乱し、路肩の路盤の土が大きくえぐり取られていた。崩落の復旧工事も遅れ気味で、開通はいつになるか判らないようだ。

コグルミ谷は、 元々、土石流などで谷道が荒れ、道筋がよく変わるところであったのだが、予想をはるかに超える様変わりであった。登山口周辺には、谷筋から多量に押し流されてきた土石が道路上を埋め尽くしていた。「心の谷」と刻まれた石碑は半分以上土砂に埋もれ、路肩のガイドレールもへしまがっていた。今更のように自然の脅威を見せつけられた。

今回は、写真付きでコグルミ谷で密かに群生している場所を正確に伝えてくれたので、5月31日(金)、山野草を愛でている友人を誘って出かける気になった。
このコグルミ谷に行くには、滋賀県と三重県を結んでいる国道306号線の鞍掛峠を通過しなければならない。だが、昨年9月17、18日の大雨により道路が崩落し、通行止めとなっていた。仕方なく、滋賀県側の鞍掛峠駐車場に自動車を止め、コグルミ谷 の出合にむかった。
国道306号 鞍掛峠 通行止めのお知らせの看板

滋賀側のトンネルまでは通行可能だが、三重側の道路上には土石が散乱し、路肩の路盤の土が大きくえぐり取られていた。崩落の復旧工事も遅れ気味で、開通はいつになるか判らないようだ。

コグルミ谷は、 元々、土石流などで谷道が荒れ、道筋がよく変わるところであったのだが、予想をはるかに超える様変わりであった。登山口周辺には、谷筋から多量に押し流されてきた土石が道路上を埋め尽くしていた。「心の谷」と刻まれた石碑は半分以上土砂に埋もれ、路肩のガイドレールもへしまがっていた。今更のように自然の脅威を見せつけられた。
コグルミ谷登山口


4年前 花の御池岳に行った際、グルミ谷出合を通過していたので、地形的には理解していたつもりであった。しかしながら、一歩谷筋に足を踏み入れると、全くコースがわかりにくくなっていた。
谷底の土砂はほとんど流され、堆積していた小石も無くなり石灰石の露岩がむき出しとなっていた。また両脇の土壌もえぐり取られ、各所で倒木がひどい。 コグルミ谷はほんの少し右側にわん曲しているのだが、前進できるところを探しながら登って行った。20~30分進んだところで、コグルミ谷の右岸尾根筋に入ってしまったことに気が付き、左側の谷筋に降りようとしたが、えぐれる様になった谷には降り切れなかった。
その結果、コグルミ谷に足を踏み入れることなく終わってしまった。あれだけ期待していたクマガイソウにも出会うことができなかったのは非常に残念であった。尾根筋を高まきすれば何とかなるだろうと安易な判断が猛省される。


GPSの軌跡で辿ったルートをひらって見た。スタート地点から点線で示した従来のコグルミ谷ルートから逸れてしまっていた。途中、標高800m地点の高台状のところで青いテープ の目印を見つけ、それに導かれて一般道のカタクリ峠(6合目)に到達。この間、以前1時間15分程度であったが、道なき森林帯のルートファイティングを強いられ3時間強の時間を要した。
もと来た道を辿るのも面白くないので、白船峠方面に寄り道して鈴北岳を経由して鞍掛峠へ下山した。この時期、やまヒルを心配していたが、全く出会わなかったのが、唯一の成果であった。今回は不発に終わったが、来年再挑戦だ。
今回辿ったGPSの軌跡

カタクリ峠(6合目)

クマガイソウには出会えなかったが、コグルミ谷で友人が撮った写真を添付した。
数日前、彼女達は、御池岳周辺でクマガイソウが自生していると思われる3か所に目をつけて探しに来ていた。その内の一か所で見つけたものである。
友人が撮影したクマガイソウ












