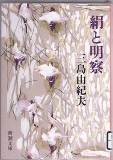2010年03月10日 いまなぜ蟹工船
[蟹工船ブーム] ブログ村キーワード
小生、高校生の時「おい、地獄さ行ぐんだで!」という言葉で始まる[蟹工船」を読んだ。当時、親戚の大学生の姉さんから「何でそんな小説を読んでいるの」と言われたことがあった。

この蟹工船と言うタイトルが気に入り、文庫本のカバーが赤と黒の刺激的なデザインであった。ただ、それだけの理由で読み出した。作者小林多喜二は、29歳で命を落とした青年で、プロレタリア作家であることは知っていた。
オホーツク海に向かっていく蟹工船…、妙に「糞壷」の言葉だけが、長年深く頭に沁みついていた。
どうしょうもなく荒れ狂い、凍てつく海の様々な姿とすえた臭いがする「糞壷」の様子が幾度となく描かれていた。工船と言う逃げ場のない完封された世界を舞台して、働く労働者の姿を克明にえぐりだしていた。
昭和初期には、大不況に直撃された。農夫・炭鉱工夫・肉体労働者の出稼ぎ労働者が集められ、 カムチャツカの沖で蟹を獲り、船上で缶詰に加工する工場施設を備えた工船 ...。外貨獲得の高価な製品を生み出しているにも拘わらず、船主である大会社の資本家達に、人間的権利まで剥奪されて酷使された。日本が辿ってきた近代の歴史であり、当時の秘められた社会構造のひずみを垣間見る事が出来た。
2008年、蟹工船が、新語・流行語大賞でトップ10に選ばれた。格差社会、世界的不況といった世相を反映したものである。 同年1月、ある対談で、フリーター、日雇派遣、ネットカフェ難民などの集会やデモに参加し、ワーキングプアの実態を知っていた作家雨宮が「蟹工船の描く世界が現在のフリーターの状況と似ている」との発言があった。
とある書店さんがこの記事を読んでピンとくるものがあって、「平台に置いてみると1週間に30冊、40冊と売れ始めたのが始まりである」と言われている。その後、全国紙が大きく取り上げ、蟹工船ブームが一気に爆発した。「蟹工船・党生活者」は、50年間に100万部の売り上げを記録し、最近は年間5千部の売れ行きだったが、2008年は1年間だけで50万部に迫る売り上げとなった。
「蟹工船」の読者は圧倒的に若者だそうだ。フリーター・ワーキングプアの人々は、蟹工船という過酷な状況を今の自分達の境遇に置き換えてみて共感を覚えたのであろう。
以前、フリーターといえば、将来の夢を持ち、人生を真剣に考える若者であった。パート・アルバイトなどの多様な働き方をしていた人々を「フリーター」と呼んでいた。だが、最近では、働く意志はあるが、正社員として就業していない人を広くフリーターとしてとらえられている。働いているのに、収入が生活保護受給水準以下である。格差社会が進み、リストラなどによって企業社会から落伍してしまうと、ふたたび浮き上がることが難しくなった社会構造になっている。
電話一本で呼び出される労働者でもあり、日単位の仕事について電話、メール等で派遣元からの指示を受け、マイクロバスに乗せられ送り込まれている。正しく、人材派遣会社の奴隷となった「現代版蟹工船」である。派遣先から仕事の依頼メールが携帯に届くと働きに出るという生活を繰り返しているのだ。
更に、定住場所を持たないネットカフェ難民は、深夜に長時間・低額料金で利用できるインターネットカフェや漫画喫茶で、寝泊まりしている。個室に仕切られた僅かなスペース、所謂「現在の糞壷」で生活を強いられている。
80年経った現在、以前の社会の本質に何ら変わっていない。今のこんな世の中だからこそ「蟹工船」が心に響くのであろ。
2008年5月2日読売新聞夕刊の一面に「蟹工船」再脚光...格差嘆き若者共感、増刷で売り上げ5倍(読売新聞) ...のタイトルが紹介されていた。特高警察の憤激を買い、拷問死させられた小林多喜二にとっては、命を張った結果がこれかよ…。いくら売れても本意でなかろう。
日雇い派遣で働く若者が悲惨な待遇を「それって蟹工じゃん」と言い合っているそうな。
小生、『蟹工船』で最も気に入っている一節。→追記をクリック

にほんブログ村
小生、高校生の時「おい、地獄さ行ぐんだで!」という言葉で始まる[蟹工船」を読んだ。当時、親戚の大学生の姉さんから「何でそんな小説を読んでいるの」と言われたことがあった。

この蟹工船と言うタイトルが気に入り、文庫本のカバーが赤と黒の刺激的なデザインであった。ただ、それだけの理由で読み出した。作者小林多喜二は、29歳で命を落とした青年で、プロレタリア作家であることは知っていた。
オホーツク海に向かっていく蟹工船…、妙に「糞壷」の言葉だけが、長年深く頭に沁みついていた。
どうしょうもなく荒れ狂い、凍てつく海の様々な姿とすえた臭いがする「糞壷」の様子が幾度となく描かれていた。工船と言う逃げ場のない完封された世界を舞台して、働く労働者の姿を克明にえぐりだしていた。
昭和初期には、大不況に直撃された。農夫・炭鉱工夫・肉体労働者の出稼ぎ労働者が集められ、 カムチャツカの沖で蟹を獲り、船上で缶詰に加工する工場施設を備えた工船 ...。外貨獲得の高価な製品を生み出しているにも拘わらず、船主である大会社の資本家達に、人間的権利まで剥奪されて酷使された。日本が辿ってきた近代の歴史であり、当時の秘められた社会構造のひずみを垣間見る事が出来た。
2008年、蟹工船が、新語・流行語大賞でトップ10に選ばれた。格差社会、世界的不況といった世相を反映したものである。 同年1月、ある対談で、フリーター、日雇派遣、ネットカフェ難民などの集会やデモに参加し、ワーキングプアの実態を知っていた作家雨宮が「蟹工船の描く世界が現在のフリーターの状況と似ている」との発言があった。
とある書店さんがこの記事を読んでピンとくるものがあって、「平台に置いてみると1週間に30冊、40冊と売れ始めたのが始まりである」と言われている。その後、全国紙が大きく取り上げ、蟹工船ブームが一気に爆発した。「蟹工船・党生活者」は、50年間に100万部の売り上げを記録し、最近は年間5千部の売れ行きだったが、2008年は1年間だけで50万部に迫る売り上げとなった。
「蟹工船」の読者は圧倒的に若者だそうだ。フリーター・ワーキングプアの人々は、蟹工船という過酷な状況を今の自分達の境遇に置き換えてみて共感を覚えたのであろう。
以前、フリーターといえば、将来の夢を持ち、人生を真剣に考える若者であった。パート・アルバイトなどの多様な働き方をしていた人々を「フリーター」と呼んでいた。だが、最近では、働く意志はあるが、正社員として就業していない人を広くフリーターとしてとらえられている。働いているのに、収入が生活保護受給水準以下である。格差社会が進み、リストラなどによって企業社会から落伍してしまうと、ふたたび浮き上がることが難しくなった社会構造になっている。
電話一本で呼び出される労働者でもあり、日単位の仕事について電話、メール等で派遣元からの指示を受け、マイクロバスに乗せられ送り込まれている。正しく、人材派遣会社の奴隷となった「現代版蟹工船」である。派遣先から仕事の依頼メールが携帯に届くと働きに出るという生活を繰り返しているのだ。
更に、定住場所を持たないネットカフェ難民は、深夜に長時間・低額料金で利用できるインターネットカフェや漫画喫茶で、寝泊まりしている。個室に仕切られた僅かなスペース、所謂「現在の糞壷」で生活を強いられている。
80年経った現在、以前の社会の本質に何ら変わっていない。今のこんな世の中だからこそ「蟹工船」が心に響くのであろ。
2008年5月2日読売新聞夕刊の一面に「蟹工船」再脚光...格差嘆き若者共感、増刷で売り上げ5倍(読売新聞) ...のタイトルが紹介されていた。特高警察の憤激を買い、拷問死させられた小林多喜二にとっては、命を張った結果がこれかよ…。いくら売れても本意でなかろう。
日雇い派遣で働く若者が悲惨な待遇を「それって蟹工じゃん」と言い合っているそうな。
小生、『蟹工船』で最も気に入っている一節。→追記をクリック
にほんブログ村
小説一節
祝津(しゅくつ)の燈台が、廻転する度にキラッキラッと光るのが、ずウと遠い右手に、一面灰色の海のような海霧(ガス)の中から見えた。それが他方へ廻転してゆくとき、何か神秘的に、長く、遠く白銀色の光茫(こうぼう)を何海浬(かいり)もサッと引いた。
留萌(るもい)の沖あたりから、細い、ジュクジュクした雨が降り出してきた。漁夫や雑夫は蟹の鋏(はさみ)のようにかじかんだ手を時々はすがいに懐(ふところ)の中につッこんだり、口のあたりを両手で円(ま)るく囲んで、ハアーと息をかけたりして働かなければならなかった。――納豆の糸のような雨がしきりなしに、それと同じ色の不透明な海に降った。が、稚内(わっかない)に近くなるに従って、雨が粒々になって来、広い海の面が旗でもなびくように、うねりが出て来て、そして又それが細かく、せわしなくなった。――風がマストに当ると不吉に鳴った。鋲(びょう)がゆるみでもするように、ギイギイと船の何処かが、しきりなしにきしんだ。宗谷海峡に入った時は、三千噸(トン)に近いこの船が、しゃっくりにでも取りつかれたように、ギク、シャクし出した。何か素晴しい力でグイと持ち上げられる。船が一瞬間宙に浮かぶ。――
Posted by
nonio
at
12:20
│Comments(
0
) │
書籍
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。