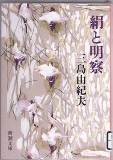2009年08月13日 いまなぜ太宰治
NHKクローズアップ現代(2009年6月22日放送) にて「生誕百年 太宰治はなぜうける作家…」について井上ひさし, 国谷 裕子によるTVが放映された。
世を去って60年以上経つにもかかわらず、太宰治の作品群は現代の若者層に異様なほどの人気を誇っています。代表作「人間失格」は、昨年の発行部数が前年の5倍に、「走れメロス」は7倍に。また、戦後の売り上げは新潮文庫だけでも累計600万部を突破しており、夏目漱石の『こころ』と何十年にも渡り累計部数を争っています。
特に、中高生の読書感想文に、教育現場では敬遠されがちの『人間失格』が圧倒的に多く、大学の卒論にも太宰を取り上げているようです。また、「走れメロス」は教科書にも掲載され、多くの人達に読まれています。
太宰治は津軽の屈指の大金持ちの生まれ。彼は、凶作の度に百姓に金を貸し、土地を召し上げた新興大地主に反発、津軽と言う田舎ものに劣等感を持っていた。東京帝国大学に入学するが、放蕩に明け暮れ、家から勘当をいい渡された。太宰は、家庭を顧みず、乱れた破天荒な生活に明け暮れた。
「人間失格」は、これまで犯してきた自分の恥の総決算として執筆に取りかかり、昭和23年5月12日脱稿。そのおよそ1ヶ月後、太宰は玉川に入水心中し、愛人・山崎富栄とともに生命を絶つ数奇な運命を辿った。
39年の生涯で4回の自殺未遂を繰り返しながら、小説を執筆してきた。太宰が退廃的で極限の世界を描くとき、同じ境遇にならなければ真の小説は書けないと考え、人間の根幹にかかわる「生死」を描くために、実際に「生死」をさ迷っています。
では、太宰治の「人間失格」の一節を示します。実に多岐にわたって悩むのです。
「隣人の苦しみの性質、程度がまるで見当つかないのです。」ここから、読点「、」はありますが、句点は「。」まで長い一節になっています。
「プラクテカルな苦しみ、ただ、めしを食えたらそれで解決できる苦しみ、しかし、それこそ最も強い苦痛で、自分の例の十個の禍など、吹き飛んでしまう程の、凄惨な阿鼻地獄なのかもしれない、それは、わからない、しかし、それにしては、良く自殺もせず、発狂もせず、政党を論じ、絶望もせず、屈せず生活のたたかいを続けていける、苦しくないんじゃないか?エゴイストになりきって、しかもそれを当然のことと確信し、いちども自分を疑ったことがないんぢゃないか?それなら、楽だ、しかし、人間といふものは、皆そんなもので、……考えれば考えるほど、自分にはわからなくなり、自分ひとりまったく変わっているような、不安と恐怖に襲わればかりです」
途中割愛していますが、ひとつの文章は20から50字ぐらいが理想とされています。だが、約1000文字。ここまで長くなると、主語がどれで述語がどれか分からなくなってきます。 しかし、長い文章によってしか獲得できない文学的効果を狙っているのでしょう。
「自分には、禍のかたまりが十個あって、その一個でも、隣人が背負ったら、その一個だけでも充分に隣人のいのちとりになるのではあるまいかと、思った事さえありました」続けて、「めしを食えたらそれで解決できる苦しみ」と、とにかく、大した悩みでもないのに大袈裟に話が展開します。
ひとつを語るのに、「ああでもない、こうでもない」と色んな側面から、くどいほど表現されています。浮かんでくる言葉をとりとめもなく、読点だけで、次から次に続けどんどんつないでいくように見えます。実際の太宰の原稿は、単純に言葉を繋いだわけではなく、文章を推敲されているのですが…。
この文体は、若者のブログの中で見かけると指摘されています。女子学生が、とり止めもなく、しやべっているようだとも言われています。したがって、太宰の小説は、若者にとって馴染みやすい文体であるので、違和感なく受け入れられるようです。且つ、共通した悩みを一緒に悩んでくれているように思うのでしょう。
更に、読んでいて気づいたことですが、太宰治は、主人公の名を借りて、自分を語っているのですが、一方では、読者に向かっても語りかけてくるのです。この語り口は、何回も繰り返して不安と恐怖の悩みや葛藤を、文字の向こうにいる読者に向かっているのです。
特に社会との違和感を持っている多情な若者達にとっては、自分にだけに語りかけてくるように誘い込まれ、手放しで心酔してしまうようだ。 この語り口は、太宰小説の真骨頂であり、現代の若者に支持されているところのようです。
小説は、「恥の多い生活を送ってきました」からはじまります。彼の生き様と相まって、「恥の多い生活」との言葉から出発したのでしょうか。
「原文では「私」を消して「自分」として代えられていますが、より親近感を持たせたのでしょう。手記全体にわたりその一人称が使われ、主人公大庭葉蔵の語る過去には、太宰自身の人生を色濃く反映したと思われる部分が多々あり、自伝的な小説ともいわれています。
大庭葉蔵は、女性遍歴で様々の女に惚れられ、破滅していく男の心の動きを自ら語っていきます。はしがきは第一の手記、第二の手記、第三の手記からなっています。繊細な感覚の持ち主で、人と会話が出来ないため、他人の前で道化を演じてみせることで人と繋がることが出来たと言います。
それで結果として、欺瞞的な人たちに対しては、孤独を選択していきました。葉蔵の名前を借りて、太宰自身の性格を語っているのかもしれませんが、『人から与えられると自分の好みに合わなくても拒むことができない、この性格が「恥の多い生涯」の原因になっていると振り返っています』。性格はもどかしいほど弱々しく語ると思いきや、慇懃無礼な態度もとり、ナイーブで複雑です。
何より表現が大げさで、かつ些細なところでこだわる主人公に、どう対応すればよいのか戸惑ってしまいます。それも語り口が、淡々と軽妙な文体で語ってくるのです。
旧制高校に進学してからは、人間への恐怖を紛らわすために悪友についてまわり、酒とタバコと淫売婦と左翼運動に走り、やがてゆきずりの女性と心中未遂事件を起こし、自分だけが生き残ってしまうのです。
葉蔵は「淫売婦たちと遊んでいるうちに、いつのまにやら、忌まわしい雰囲気を身辺にいつもただよはせる…」と嘆いていますが、いつの間にか底辺の世界に馴染んでしまい。「貧乏くさいだけのツネ子に親近感が胸にこみ上げ…微弱ながら恋の心の動くのを自覚しました。」
そして葉蔵は、いとも簡単に死の提案に気軽に同意します。
「女の人は、死にました。そうして自分だけ助かりました」と淡々と自殺の場面を描いています。
それも、この「貧乏くさいツネ子から」と表現していますが、この言葉は、小説を面白く演出するためか。それとも太宰がこのような女に安らぎを覚え、世間の苦悩から断ち切りたかったのか、小生では、どのような態度を取ったか…。色々考えされる場面です。つまり、これは太宰のことを語っているのか、作り物なのか、詮索しながら読み進めることが出来、面白い。
そして、葉蔵の心情も語っています。「実感としての『死のう』と言う覚悟はできていなかったのです。どこかに「遊び」がひそんでいました」と付け加えています。そこまで語るのかと言うより、作家太宰の純粋で正直な性格が現れているように思えた。
いずれにしても、「死」の臭いがする世間とはずれた特異なテーマを題材としていますが、葉蔵自身の性癖なのか、人生の下降線をへらへら辿っていく姿を、陰惨さはなく面白く、且つ物悲しく描かれています。貧乏くさいツネ子の言葉には、より一層哀れみを誘い、その中に、太宰治の影も、ちらついてくるように思えた。特に、太宰はこの「人間失格」の小説のなかで、「侘しい」と言う言葉は恐怖・不安から離れることが出来るとして大切にしていたことが味わい深く、印象がつよい。
その後、大庭葉蔵は、子持ち女性やスタンド・バーのマダム等と明日の無い生活にはまり込み、だんだんと人生が絶望的な状況になっていった。その果てには内妻ヨシ子が小男の商人に、犯されます。「自分の若白髪は、その夜からはじまり、いよいよ人を底知れず疑い、この世の営みに対する一切の期待、よろこび、共鳴などから、永遠になれるようになりました。実に、それは自分の生涯に於いて決定的な事件でした。…」「神に問ふ。信頼は罪なりや」「果たして、無垢の信頼心は、罪の源泉なりや」「無垢の信頼は、罪なりや。」神の答えは得られるままに…」と悩み抜きます。
葉蔵はアルコールを浴びるほど飲み、その勢いで睡眠薬を用いて発作的に自殺未遂を起こしました。助かったものの酒に溺れるようになり、その後、薬に走りモルヒネ中毒となり、実家に金を無心するようになりました。やがて葉蔵は脳病院へ入院させられます。ここで葉蔵は、狂人として扱われたと思い、「もはや、自分は、完全に人間でなくなりました」つまり人間失格だと悟るのです。
以上が「人間失格」のあらすじですが、なんとも不思議な世界に引き込まれてしまいました。
最後に残した言葉に、「今は、自分には、幸福も不幸もありません。…人間の世界に於いて、たった一つ、真理らしく思われたのは、それだけでした。ただ一さいは過ぎていきます。自分は今年、二十七になります。白髪がめっきりふえたので、たいていの人から四十以上にみられます」と言う手記で終わっています。