2008年07月17日 オオヤマレンゲを求め大峰山
日付7月4日(土)〜5日
コースタイム
行者環トンネル西口6:30 大峰奥駈道分岐7:40 弁天の森8:05 聖宝の宿跡8:40
弥生9:50 八経ケ岳10:40 弥生11:50〜12:30 大峰奥駈道分岐 13:35
行者環トンネル西口14:40
大峰山の山行きには因縁がある。2006年から天候不順で中断されてきた。今年で4回目である。今年も梅雨のまっただなかで半ば諦めていた。ところが、7月3日、天気予報は、奈良の降水確率5日30%・6日20%と俄然期待が持てるようになり、出発した。
オオヤマレンゲは、梅雨から7月にかけて花目を開花させ、かぐわしい香りを放つ清楚で気品のある花である。「天女の花」とか「森の貴婦人」呼ばれている。
「天女の花」と呼ばれている オオヤマレンゲ

7月4日、行者環トンネル西口の少し上がった広場でテント泊した。知り合いの奈良の
山クラブと合流し、阪神タイガースS選手(器用でバントも巧い)の父親とも歓談し、
大いに盛り上がった。
地図を読むと出発点から、近畿最高峰八経ケ岳(1914.9m)までの行程で苦しい
箇所は、二つある。そのひとつが、これから向かう大峰奥駈道分岐までの登りである。
標高差にして約380mの急登である。6:30出発した。
川沿いの登山道を歩き、吊り橋を渡ると、いよいよ1時間近くの登りが続いた。
一汗かいて上りきると、大峰奥駈道分岐に出た。
この道は、修験者が神々の道を辿り熊野へと通ずる道である。聖宝ノ宿跡までは大きな起伏
もなく、樹林帯の快適な1時間となった。

大峰奥駈道の樹林帯の歩行

大峰奥駈道の樹林帯の倒木
聖宝ノ宿跡の手前で忽然と視界が開いた。樹林帯の半ば薄暗いところから、ブルーの鮮やかな空
を背景に弥生・特徴のある近畿最高峰八経ケ岳が一瞬見ることが出来た。
この日は、周辺の大峰山系の山々には、どんよりした雲がかかっていたが、不思議とこの瞬間だけ晴れ渡った。

一瞬雲が晴れ弥生の山容の眺望

近畿最高峰八経ケ岳
いよいよ、聖宝ノ宿跡 から弥生小屋までのふたつめの胸突き八丁が始まった。
標高差にして310m時間にして1時間強であった。整備された木の階段を登り詰めると人気がする
弥生小屋に着いた。
弥生・八経ケ岳の遠望 弥生小屋を通り過ぎ右手の鳥居を潜って頂上に向かった。
トウヒの立ち枯れの惨状は、痛々しい 。トウヒは、常緑針葉樹で「もみの木」 に良く似た マツ科の変種である。
たぶん、大峰山は、有数の多雨地帯であるため、酸性雨の影響もうけるのであろう。
その上、僅か、3時間弱で、八経ガ岳まで登れる日帰りハイキングコースとなっていた。
このため、観光ツアー・アウトドワツワーの団体客が押し寄せてきていることも遠因のひとつであろう。
ここは、既に聖地ではなかった。

トウヒの立ち枯れの惨状

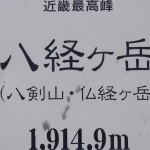
弥生 八経ケ岳

近畿最高峰八経ケ岳からのながめ
コースタイム
行者環トンネル西口6:30 大峰奥駈道分岐7:40 弁天の森8:05 聖宝の宿跡8:40
弥生9:50 八経ケ岳10:40 弥生11:50〜12:30 大峰奥駈道分岐 13:35
行者環トンネル西口14:40
大峰山の山行きには因縁がある。2006年から天候不順で中断されてきた。今年で4回目である。今年も梅雨のまっただなかで半ば諦めていた。ところが、7月3日、天気予報は、奈良の降水確率5日30%・6日20%と俄然期待が持てるようになり、出発した。
オオヤマレンゲは、梅雨から7月にかけて花目を開花させ、かぐわしい香りを放つ清楚で気品のある花である。「天女の花」とか「森の貴婦人」呼ばれている。
「天女の花」と呼ばれている オオヤマレンゲ

7月4日、行者環トンネル西口の少し上がった広場でテント泊した。知り合いの奈良の
山クラブと合流し、阪神タイガースS選手(器用でバントも巧い)の父親とも歓談し、
大いに盛り上がった。
地図を読むと出発点から、近畿最高峰八経ケ岳(1914.9m)までの行程で苦しい
箇所は、二つある。そのひとつが、これから向かう大峰奥駈道分岐までの登りである。
標高差にして約380mの急登である。6:30出発した。
川沿いの登山道を歩き、吊り橋を渡ると、いよいよ1時間近くの登りが続いた。
一汗かいて上りきると、大峰奥駈道分岐に出た。
この道は、修験者が神々の道を辿り熊野へと通ずる道である。聖宝ノ宿跡までは大きな起伏
もなく、樹林帯の快適な1時間となった。

大峰奥駈道の樹林帯の歩行

大峰奥駈道の樹林帯の倒木
聖宝ノ宿跡の手前で忽然と視界が開いた。樹林帯の半ば薄暗いところから、ブルーの鮮やかな空
を背景に弥生・特徴のある近畿最高峰八経ケ岳が一瞬見ることが出来た。
この日は、周辺の大峰山系の山々には、どんよりした雲がかかっていたが、不思議とこの瞬間だけ晴れ渡った。

一瞬雲が晴れ弥生の山容の眺望

近畿最高峰八経ケ岳
いよいよ、聖宝ノ宿跡 から弥生小屋までのふたつめの胸突き八丁が始まった。
標高差にして310m時間にして1時間強であった。整備された木の階段を登り詰めると人気がする
弥生小屋に着いた。
弥生・八経ケ岳の遠望 弥生小屋を通り過ぎ右手の鳥居を潜って頂上に向かった。
トウヒの立ち枯れの惨状は、痛々しい 。トウヒは、常緑針葉樹で「もみの木」 に良く似た マツ科の変種である。
たぶん、大峰山は、有数の多雨地帯であるため、酸性雨の影響もうけるのであろう。
その上、僅か、3時間弱で、八経ガ岳まで登れる日帰りハイキングコースとなっていた。
このため、観光ツアー・アウトドワツワーの団体客が押し寄せてきていることも遠因のひとつであろう。
ここは、既に聖地ではなかった。

トウヒの立ち枯れの惨状

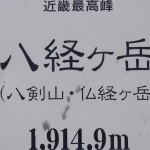
弥生 八経ケ岳

近畿最高峰八経ケ岳からのながめ
Posted by
nonio
at
09:00
│Comments(
0
) │
近隣の山










